
ブログを書いたり、パソコンで動画を観たりしていると、気づけば肩や腰がパンパン…なんて経験、ありませんか?
私自身、ブログ執筆がいつのまにか数時間経っていて、立ち上がった瞬間に「いたたた……」と背中をさすったことが何度もあります。
パソコン作業で疲れてしまう原因は、単に「長時間使っているから」だけではありません。
座りっぱなしの姿勢、目線の角度、手の動きや椅子の硬さなど、作業環境の小さなズレが積み重なって、疲れや不調につながっているのです。
でも、安心してください。
ちょっとしたグッズを取り入れるだけで、パソコン作業が驚くほど快適になり、疲れにくくなります。
今回は、ブログ初心者の方や在宅ワークをされている方にもぴったりな「疲労軽減×快適度UP」な神グッズを3つご紹介します!
グッズ①:ノートパソコンスタンド
まず最初におすすめしたいのが、ノートパソコンスタンドです。
パソコン作業で首や肩が疲れる理由のひとつが、ノートPCをそのまま机に置いて使うこと。これ、実は目線が自然と下がって猫背になりやすいんです。
猫背になると、首が前に出て、肩や背中に大きな負担がかかります。
これが長時間になると、肩こり・首の痛み・集中力の低下に直結。
でも、スタンドでノートPCの位置を数センチ持ち上げるだけで、目線が上がり、自然な姿勢で作業ができるようになるんです。
さらに、スタンドを使うとパソコン底面の放熱性が向上し、動作も安定。
特に夏場や高負荷な作業をするときには熱がこもりがちなので、放熱のメリットは大きいです。
筆者が愛用しているのは、アイリスオーヤマの「ノートパソコンスタンド ポータブルタイプ NPS-P」。
価格は2000円前後と導入しやすく、折りたためば持ち運びも可能。
リモートワークや外出先での作業にもぴったりです。
また、この製品はサクラレビューをチェックできるサイト「サクラチェッカー」でも高評価。

「安くて便利だけど、実は品質がイマイチ…」というリスクを避けたい方にも安心です。
スタンドを導入するだけで、作業姿勢が改善されるだけでなく、机の上もすっきり整い、集中しやすい環境が手に入ります。
外付けキーボードと併用すれば、まるでデスクトップのような快適さ。ノートPCユーザーにはぜひ試してほしいアイテムです。
グッズ②:トラックボールマウス
続いてご紹介するのは、トラックボールマウス。
「マウスなんてどれも同じじゃない?」と思う方もいるかもしれませんが、作業効率や体への負担に大きく関わってきます。
通常のマウスは、カーソルを動かすたびに肘や肩を使ってマウス全体を移動させます。
これを長時間繰り返すことで、肩まわりや前腕の疲れ・張り感の原因になります。
一方で、トラックボールマウスは、マウス上部のボールを指で転がして操作するタイプ。
本体を動かさずに指先だけでカーソルを操作できるため、肩や腕への負担が激減します。
私が使っているのは、ELECOMの「M-DT2UR」という機種。
このマウスには、複数のショートカットボタンが自由に設定できる機能が付いており、「コピー」「貼り付け」「進む・戻る」などよく使う動作を指1本で素早く行えるようになります。
実際に使ってみると、作業効率が体感で1.5倍くらいにアップ。
ブログの執筆や画像編集などで、右手の疲れを気にせずサクサク進められるようになりました。
さらにこのモデルはUSB接続で安定感がありながらも比較的コンパクトなので、ノートパソコンスタンドと一緒に持ち運んで、リモート作業でも大活躍中です。
ボール部分にホコリがたまることがありますが、掃除もボールを外して布で拭くだけで数分で完了。
通常のマウスと大きく価格が変わらないため、肩こりが気になる人には、ぜひ一度試してほしい快適グッズです。
グッズ③:背もたれ付きのワークチェア
3つ目にご紹介するのは、背中をしっかり支えてくれるワークチェアです。
「いやいや、椅子なんて何でもいいでしょ」と思う方も多いかもしれません。
実際、以前の私もその一人で、数千円のシンプルな回転チェアを使っていました。
ところが、ある日思い切ってニトリの「ワークチェア タンパ3」に買い替えてみたところ、作業中の疲労感がまるで別物に。
背中のラインにぴったりとフィットする形状で、背もたれに体を預けても自然な姿勢がキープされるため、腰や肩への負担が激減されました。
また、リラックスしながら動画鑑賞をするときにも快適で、背中全体を包み込むようなサポートが心地よく、まるでソファに座っているかのよう。
長時間のブログ執筆後の、音楽を聴きながらのリフレッシュにも重宝しています。
現在「タンパ3」は残念ながら製造終了してしまいましたが、背中にパッドがついていて、肘掛けがあるタイプのチェアであれば、同じような効果が期待できます。
具体的には、ニトリなど家具メーカーのオフィスチェアやゲーミングチェアの一部モデルにも、背面がしっかりしていて、長時間の姿勢保持をサポートする構造のものがあります。
価格帯としては、2万円〜3万円以上と高く感じるかもしれませんが、これは“家具”というより“健康投資”。
腰痛で整体やマッサージに何度も通うことを考えれば、1つ持っておくだけで十分に元が取れるレベルの費用対効果です。
とはいえ、「いきなり2〜3万円の椅子はちょっと…」という方も多いと思います。
そんな場合は、固めのクッションを背もたれと腰の間に挟んで、腰で支える姿勢を作るだけでも、かなり楽になります。
市販の腰用クッションや、家にあるちょっと厚めのタオルなどでも代用可能なので、「今あるもので工夫したい派」の方にもおすすめです。
椅子は毎日何時間も座る「作業の土台」。
だからこそ、ここを見直すと集中力・快適性・疲労感すべてが一気に改善します。
「疲れやすい」「集中できない」と感じている人ほど、椅子を変えるインパクトを実感できるはずです。
【まとめ】疲れを減らすグッズは“自分に合ったもの”から始めよう
今回ご紹介した3つのグッズは、どれも
「パソコン作業の疲労軽減」
「快適な作業環境の構築」
に大きく貢献してくれるアイテムばかりです。
とはいえ、すべて一気にそろえる必要はありません。
たとえば、
「目線が下がって首がつらい」
→ ノートパソコンスタンド
「肩や腕がこる」
→ トラックボールマウス
「腰や背中が痛い」
→ 背もたれ付きのチェア
このように、まずは自分が今一番つらさを感じている部分から導入してみるのがおすすめです。
今回紹介したグッズのうち、スタンドとマウスは数千円で手に入りますし、椅子も長く使えばコスパは非常に高いです。
身体への負担が減るだけでなく、集中力が高まり、作業スピードやクオリティも自然と向上します。
気になったアイテムがあれば、ぜひチェックしてみてください。
あなたのパソコン作業が、もっと心地よいものになりますように。
本ブログのリラックス・体調管理カテゴリーでは、ほかにもうつ病の方がリラックスするのに役立つ情報を発信していますので、ぜひご覧ください!
👉X(旧Twitter)でも情報発信中 !
記事が気に入ったら、シェアしていただけるととても嬉しいです。



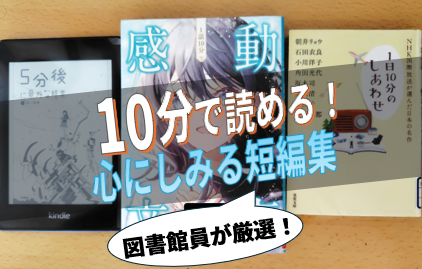





























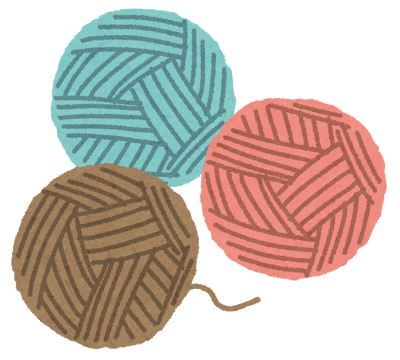


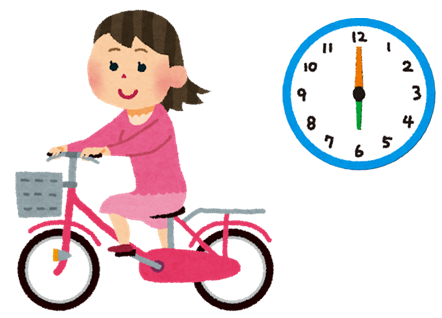













![おたふく手袋(Otafuku Glove) 夏用インナー 長袖 丸首 ファーストレイヤー[吸汗速乾 メッシュ 消臭 通気性 ストレッチ素材]JW-715 ホワイト Mサイズ おたふく手袋(Otafuku Glove) 夏用インナー 長袖 丸首 ファーストレイヤー[吸汗速乾 メッシュ 消臭 通気性 ストレッチ素材]JW-715 ホワイト Mサイズ](https://m.media-amazon.com/images/I/31chCLROehL._SL500_.jpg)



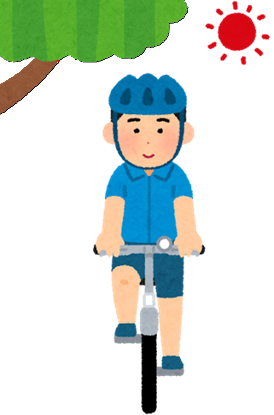






 近年はハンディファン(携帯扇風機)が定番となっていますが、筆者は昔ながらのうちわを愛用しています。
近年はハンディファン(携帯扇風機)が定番となっていますが、筆者は昔ながらのうちわを愛用しています。
























